こんにちは。 非常勤講師の「たゆ」です。
そろそろ新年度の配属などがわかり、授業の準備を進めている非常勤講師の先生も多いのではないでしょうか。
僕も去年に比べるとだいぶ授業数が減ることになりました。。。💦
少子化・私学無償化など様々な要因が考えられますがそんなことに文句を言っている時間はありません。
いまやらなくてはいけないのは、自分が担当する生徒に授業を伝えることができるかが重要だと思っています。詰め込み教育ではなく、主体的な学習を目指す授業展開を考えないといけない。。。
とは、いうものの授業の内容を教える側の人間がきちんと理解をしていないと良い授業はできないと思います。そこで今回は授業を行う上で絶対に必要な教材研究について僕なりの行い方をご紹介したいと思います。
まずは教科書を読むべし
普通でしょ。そう思うかもしれませんが教科書を読んでみることが一番大切なのではないでしょうか。
僕は地歴・公民科の非常勤講師ですが、担当する教科の教科書を必ず目を通します。正直、僕はそんなに賢くないので某会社の教科書を読んでも難しい表現が多くて難しく感じることも多くあります。
- 教科書を1度読む
- 分からないところをマーカーする
- 指導書・副教材・文献・インターネットで調べる
- もういちど教科書を読む
- スマホで録音してみる
これは絶対に行っています。もう一度読んでわからなければ再度調べるということを行うようにしています。
分からないところはマーカー
学校によっては教科書を返却しなくてはいけない学校もあると思います。ただ、授業をしていくうえで教師もすべてを知っているわけではないので、教科書を読んでみてわからないところは線を引くことをお勧めします。
そして次のステップへ
分からないのであれば調べる
これも当たり前のことだと思います。わからないのに授業で説明することなど絶対にできません。
教育実習の時にお世話になった指導教諭に言われたことで忘れることができない言葉があります。
「たとえ昨日の教材研究で知ったことでも、授業ではすごく前から知っているかのよう話せ」
正直、ごまかしの授業のような表現ですが、授業ですごく前から知っているかのように話すには、やはり教材研究をきちんと行う必要があると思います。
教科書の表現では理解できないことも多いので、まずは副教材を使います。
副教材のメリット
- 写真や地図などの文章以外の情報がたくさん載っている
- 比較的、教科書より理解しやすい言葉を使っている。
副教材のデメリット
- 重い、大きい。持ち運びに不便
- 資料によっては写真などが小さくて読み取りにくい
以上のことがあげられます。
副教材はもちろん授業でも使うので授業を展開するときに、もう少し詳しく説明したいなって時に資料を用いながら説明ができるかもしれません。
二つ目は、学習参考書
僕がよく参考にする本は、実際の授業を記録し書籍化しているものを読みます。このようなタイプの本は実際の授業のときにもまねをして進めることができます。あくまでもまねなのでオリジナルではないです。
でも、一番大切なのは生徒が何を学んでいるかきちんと理解することなので、いいのではないかと思っています。
三つめは、インターネット
費用も掛からず手軽に調べて学ぶことができる一番利用する機会が多い方法だと思います。
でも、やはり情報リテラシーが求められます。僕が学生ぐらいのころはWikipediaは参考にしてはいけないというのを当時の先生から言われたことがあります。あの頃は、Wikipediaは嘘が書かれているなんて思っていましたが、今は詳しい情報も載っていると思います。
ただ、情報の出どころ、信ぴょう性などは自分自身で判断し、活用することが大事です
スマホで録音してみる
ある程度授業のための勉強ができたら、授業で説明を行うようにスマホで録音をしてみる。
自分の説明を聞いてみて、違和感を感じたらそこは生徒にも伝わりにくいところなので、確認をし再度伝え方を変えて挑戦してみる
まとめ
完璧な授業は不可能だと思います。でも完璧に近い授業を目指すことは可能だと思います。難しいかもしれませんが、伝える内容を先生が理解することがよりよい授業づくりには欠かせないと思います
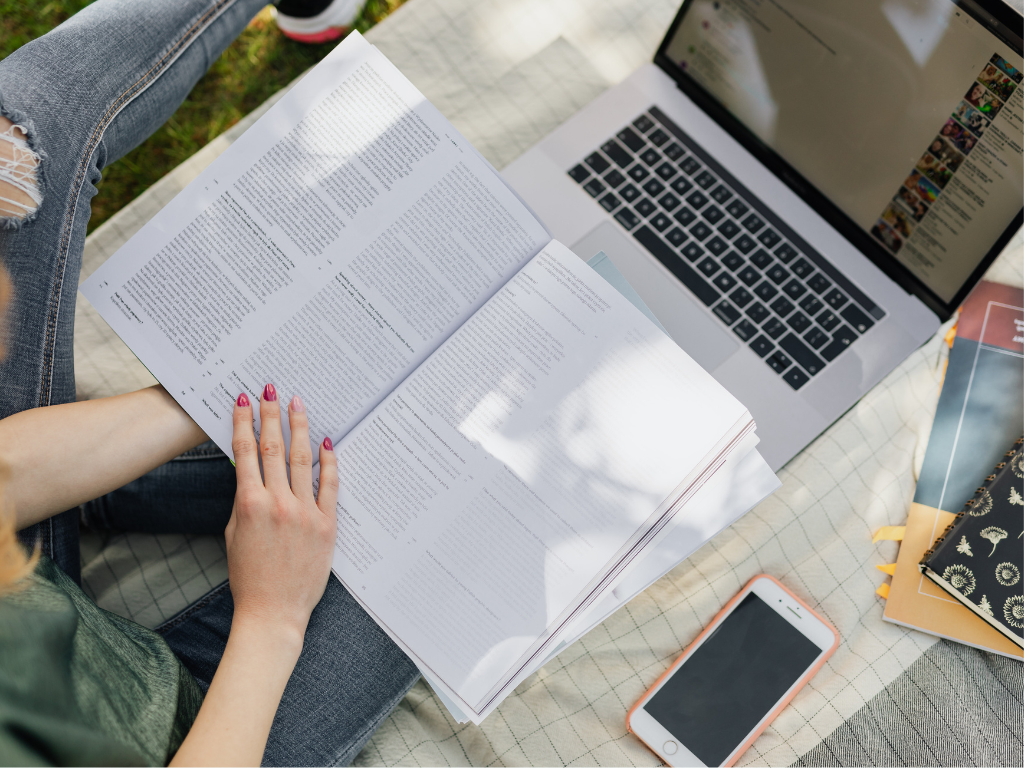


コメント